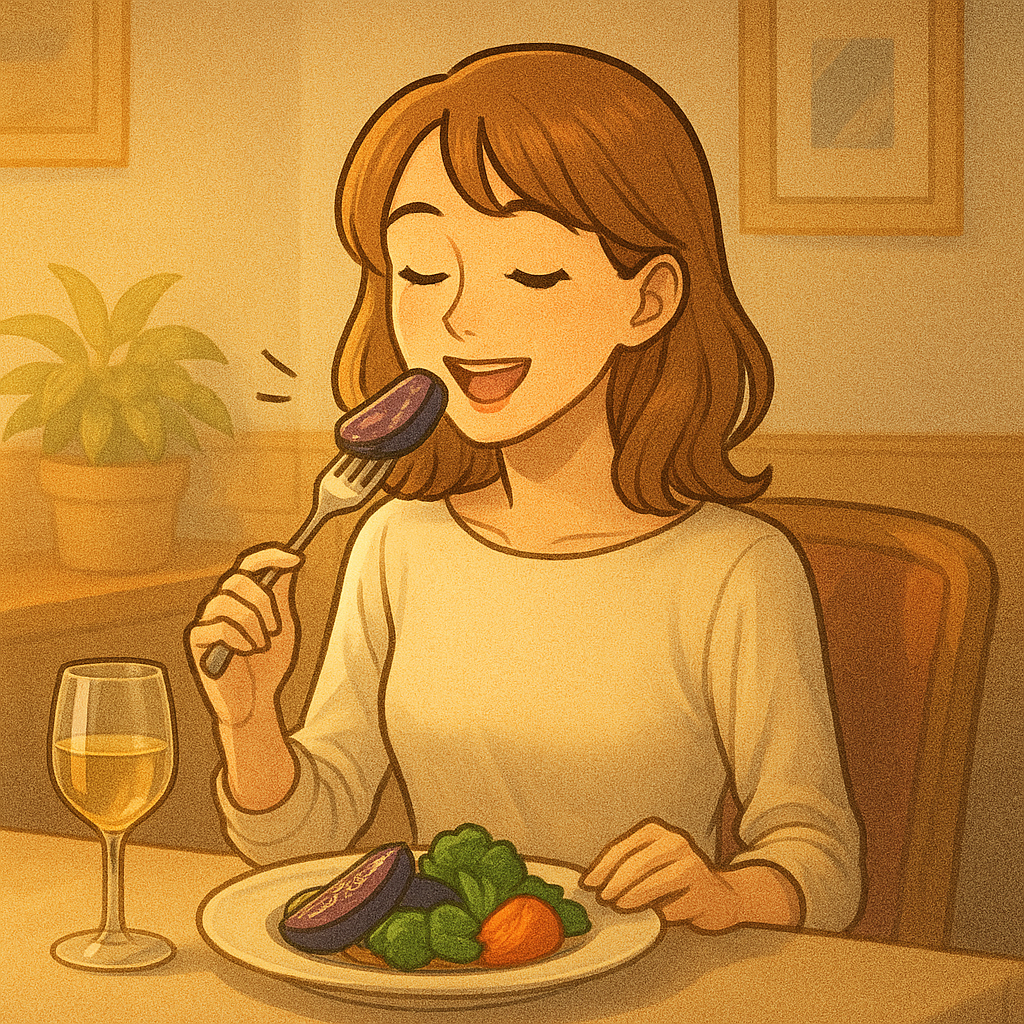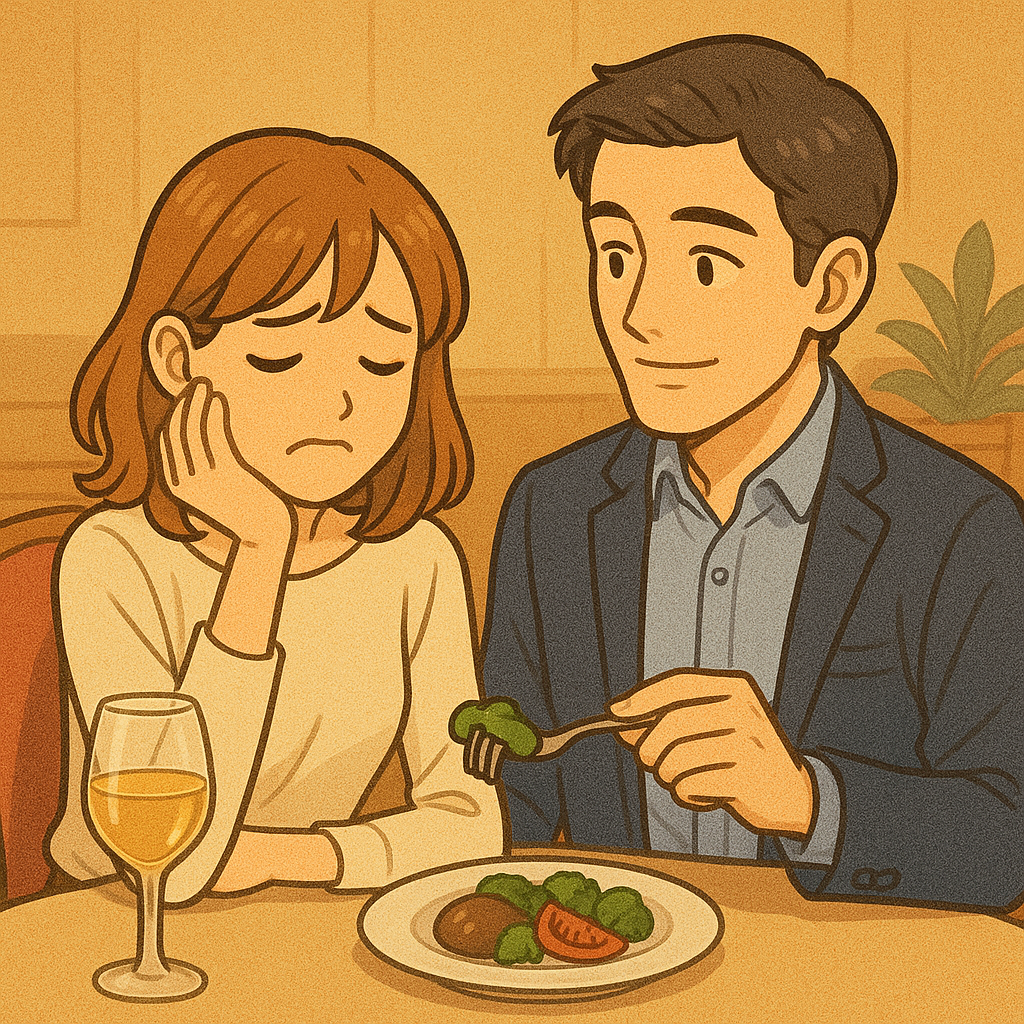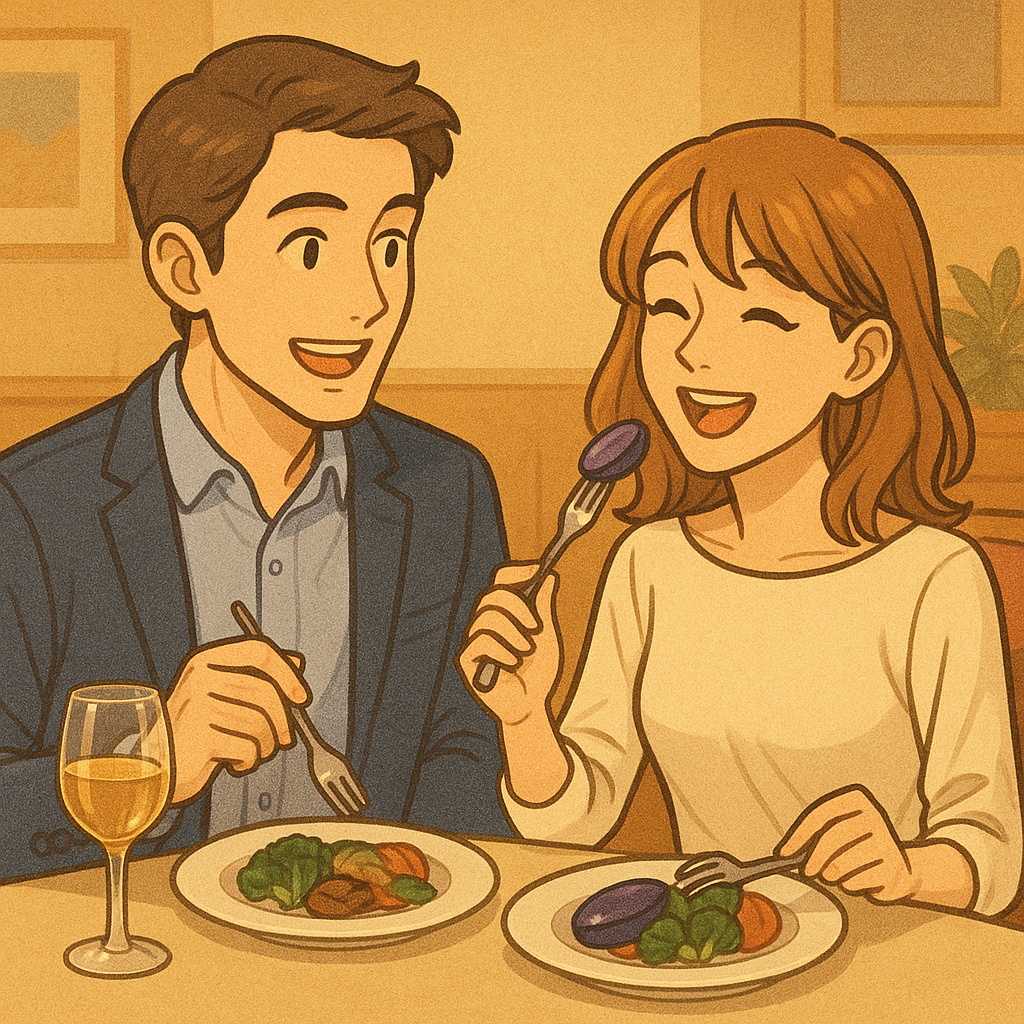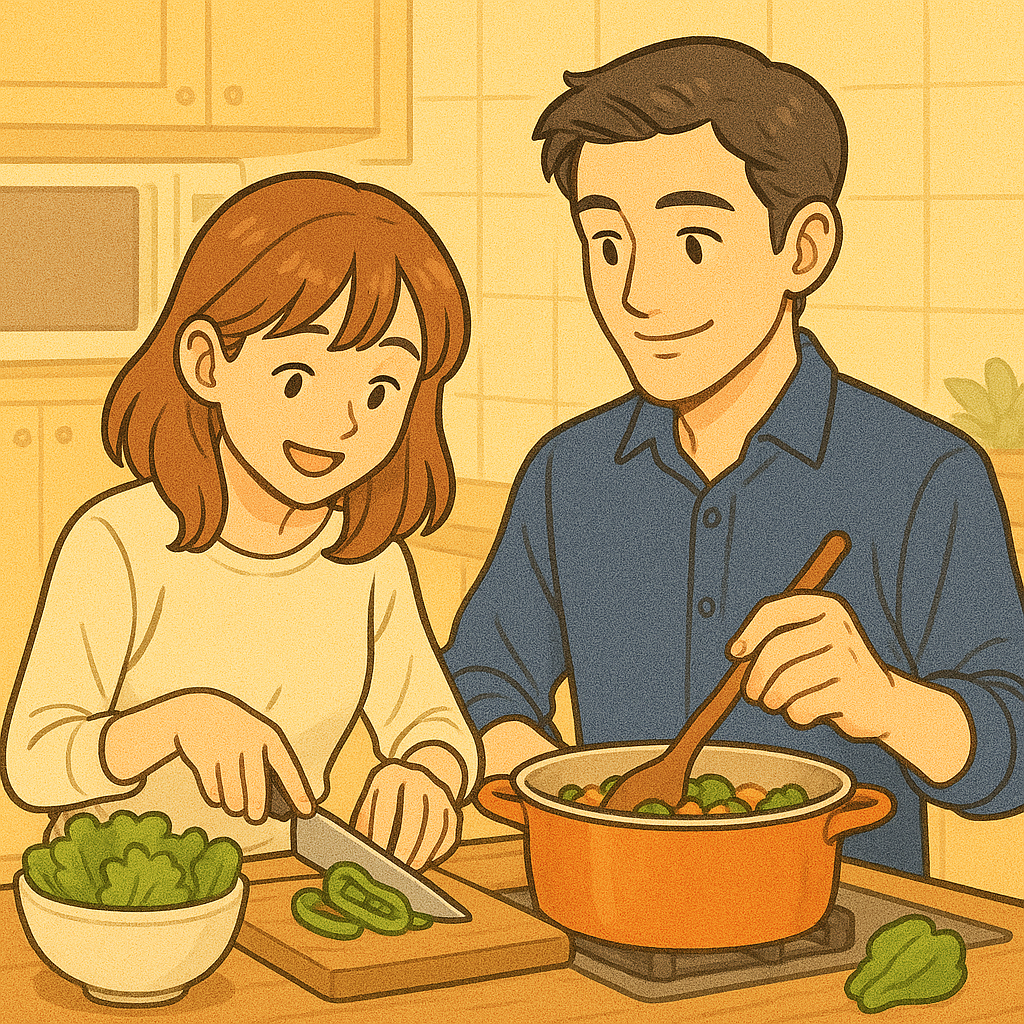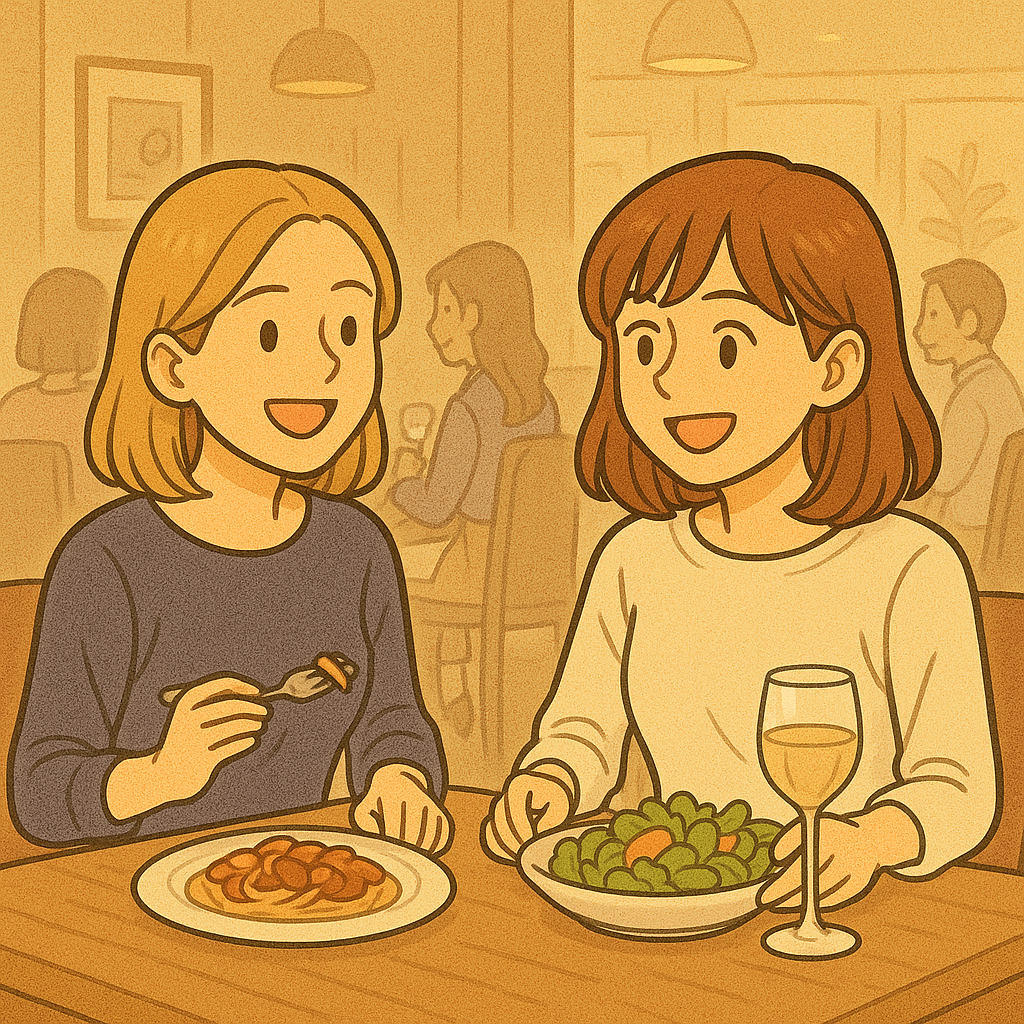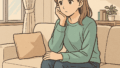「食べ物の好き嫌いが多い人」って、周りに一人はいますよね。
友達や同僚とのランチで「これはダメ」「あれも苦手」と言われると、「どうしてそんなに?」と不思議に思うことも。逆に、自分自身が「実は好き嫌いが多い…」と感じている人も少なくありません。
好き嫌いは、単なる“わがまま”や“性格の弱さ”ではなく、味覚の敏感さ・子どもの頃の食習慣・心理的な傾向・人間関係の影響など、さまざまな背景が絡んでいます。さらに統計データを見ても、大人になってからも好き嫌いを持つ人は意外と多いんです。
この記事では、好き嫌いが多い人に見られる特徴から、心理的な傾向、食べず嫌いの心理、統計データ、人間関係での一面までをわかりやすく解説します。さらに、彼や夫が好き嫌い多いときの対処法や、実際にうまくいった工夫の事例、そして「受け止め方のコツ」まで盛り込みました。
「どうしてこの人はこんなに好き嫌いがあるんだろう?」と気になっている人も、
「自分自身の好き嫌いをちょっと見直したい」という人も、
きっとヒントが見つかるはずです。
食べ物の好き嫌いが多い人に見られる特徴
味や食感にとても敏感
好き嫌いが多い人は、実は“舌のセンサー”が鋭いタイプ。
ほんの少しの苦味や酸味でも「強い!」と感じたり、ネバネバやシャキシャキなどの食感に敏感に反応します。
これは「食べ物を細かく感じ取れる才能」とも言えますよね。人によっては、グルメな一面につながることもあるんです。
子どもの頃の食習慣がそのまま大人に
幼少期の食経験は、大人になってからの好みに大きく影響します。
たとえば「実家でほとんど魚を食べなかった人は魚に抵抗がある」「小さい頃から野菜を出され続けた人は苦手が減っている」など。
子ども時代の“食の記憶”は、意外と長く心に残っているんです。
匂いや見た目へのこだわり
味そのものよりも「匂い」や「見た目」でジャッジしてしまう人も多いです。
「この匂いは苦手…」「色が鮮やかすぎて食欲がわかない」など、五感のどこかに違和感があると拒否反応につながります。
でも逆に言えば、“美味しそうに見える演出”や“食欲をそそる香り”を大切にしている、とても感覚豊かな一面でもあるんです。
安心できるパターンを好む
好き嫌いが多い人は「一度安心した食べ物」を繰り返し選びがち。
お気に入りの定食屋さんでいつも同じメニューを頼む姿を見て、「なんで毎回同じの?」と思ったことがあるかもしれません。
でもこれは「安心できるパターンを楽しんでいる」だけ。好きなものを食べる時間は、その人にとって何よりのご褒美なのです。
実は好奇心の裏返し?
一見「挑戦しない人」に見えるかもしれませんが、実は食べ物の好き嫌いが多い人は感覚が豊かだからこそ慎重なこともあります。
「未知の味に出会ったらどうなるんだろう」と考えるからこそ、一歩引いてしまう。
そう思うと、“好き嫌いが多い=臆病”ではなく、“自分の感覚を大切にしている人”とも言えますね。
.
心理的な傾向
感覚が豊かだからこそ
好き嫌いが多い人は「繊細すぎる?」と思われがちですが、実は感覚が豊かだからこそ反応しているとも言えます。
「苦味をすぐキャッチできる」「食感の違いを見抜ける」って、ある意味“食の探偵”みたいな一面。敏感さはマイナスではなく、特別な感覚の表れなんです。
安心できるパターンを大事にする
いつものメニュー、いつもの味。好き嫌いが多い人は、“安心ゾーン”を大切にする傾向があります。
それは冒険しないというより、心地よい空間をつくる工夫。お気に入りのカフェで毎回同じケーキを頼むようなものです。そこに落ち着きや喜びを感じているのです。
新しいものにちょっと慎重
「初めての食材に手を出しにくい」というのは、決してネガティブなことではありません。人間には「未知のものから身を守ろう」という本能があるからです。
好き嫌いが多い人は、この本能が少し強めに働いているだけ。つまり慎重派の冒険者とも言えるのです。
周囲の声に影響されやすい一面も
心理的な傾向として「みんなが苦手と言っていたから、自分も食べたくない」と感じることもあります。
でもこれも裏を返せば共感力が高いということ。人の気持ちに寄り添えるからこそ、食の好みにも影響を受けやすいのです。
.
好き嫌いに関する統計や一般データ
大人でも好き嫌いは多い
「好き嫌いは子どもだけ」と思いがちですが、調査では大人の約半分が「嫌いな食べ物がある」と答えているそうです。さらに「食べたことのないものは避けたい」と感じる人も3割以上いて、いわゆる“食わず嫌い”も意外と多いのが現実です。
子どもが苦手な定番野菜
子どものアンケートでは、「嫌いな野菜」としてよく名前が挙がるのが
-
ピーマン
-
ナス
-
トマト
-
ニンジン
-
ゴーヤ
など。どれも苦味や酸味、独特の食感がある食材ばかりです。小さい頃からこうした野菜に慣れていないと、大人になっても苦手意識を持ちやすいと考えられます。
年齢とともに変わる味覚
「昔は嫌いだったけど、今は食べられるようになった」という経験がある人も多いですよね。実際に大学生を対象にした調査では、9割近くの人が“以前は嫌いだった食べ物を食べられるようになった”経験があると答えています。成長や経験を通して味覚は変化し、苦手を克服する人も少なくありません。
高齢になると逆に減る食材も
一方で、高齢になると歯や噛む力、味覚や嗅覚の変化から、肉や野菜などが「食べにくい」と感じて食べる量が減ってしまうこともあります。つまり、年齢によって“食べられるもの”は増えることもあれば減ることもあるのです。
食べず嫌いは人間の本能?
「知らない食べ物を口に入れるのが怖い」という気持ちは、実は人間の自然な本能です。これを心理学では「食物ネオフォビア」と呼び、世界中で研究されています。
日本でも尺度(テストのようなもの)が作られていて、多くの人が「見たことのない食べ物はちょっと不安」と感じる傾向を持っているとわかっています。
学校給食から見える子どもの声
学校給食のアンケートでは、子どもが給食を嫌いな理由の一つに「嫌いなものが出てくるから」という答えが多く見られます。つまり、食べ物の好き嫌いは、味だけでなく「どんな場面で食べるか」にも影響されているのです。
.
食べず嫌い(食べていないのに苦手と感じる心理)
見た目や色・形からの先入観
「緑色=苦い」「黒っぽい=クセが強そう」など、見た目や色から先入観を持ってしまうことがあります。実際に食べてみる前に「自分には合わない」と判断してしまうのです。
匂いや調理法への不安
独特のにおいや、食べ慣れない調理法を見ると「口に合わないのでは」と不安になり、最初から避けてしまうこともあります。
経験がないものへの警戒心
「一度も食べたことがないから怖い」と感じるのは、人間の生存本能に根ざした自然な反応。食べず嫌いは「未知のものを避ける」心理が強く働いた結果とも言えます。
周囲の影響
親や友人が「これは苦手」「美味しくない」と言っているのを聞いて、自分も食べる前から苦手意識を持ってしまうケースもあります。特に子ども時代は、周囲の言葉がそのまま「自分の感覚」になりやすいのです。
.
人間関係での一面
ちょっと頑固?でも実は正直者
好き嫌いが多い人は「頑固」と思われがち。でも見方を変えると、自分の感覚に正直なんです。
「これは苦手だから食べない」とはっきり伝えられるのは、ある意味とても誠実な姿勢。人によっては「素直でわかりやすい人」と映ることもあります。
食事の場での“ネタ”になる
飲み会や食事会で「それ嫌いなの!?」「え〜美味しいのに!」なんて会話が生まれること、ありますよね。
好き嫌いは、場を盛り上げるちょっとした会話のスパイス。苦手があるからこそ話題になって、距離が縮まるきっかけになることもあります。
気をつかわせることもあるけれど
もちろん「せっかく作ったのに食べてもらえない」と残念に感じる場面も。
でも、好き嫌いが多い人も「申し訳ないな」と思っていることがほとんどです。
お互いに歩み寄る気持ちがあれば、小さなすれ違いも笑い話に変えられるのです。
個性として受け入れると関係がラクになる
「好き嫌いが多い=欠点」ではなく、“その人らしさ”として受け止めると関係はぐっとラクになります。
「私は好きだけど、あなたは苦手なんだね」と認め合えると、むしろお互いの理解が深まり、関係が温かくなることも。
.
彼や夫が好き嫌いが多いときの対処法
無理に直させようとしない
「せっかく作ったのに食べてくれない」「子どもみたい」とイライラしてしまうこともあるかもしれません。でも、好き嫌いはその人の感覚や経験によるもの。頭ごなしに「食べなさい!」と強制すると、余計に抵抗感を強めてしまいます。まずは「そういう特徴なんだ」と受け止める姿勢が大切です。
食べられるものをベースに工夫する
食卓を囲むときは、「食べられるもの」を中心に献立を考えるとストレスが減ります。たとえば「肉は大丈夫だけど野菜が苦手」なら、野菜を小さく刻んでスープに入れるなど、相手の“食べられるゾーン”を広げる工夫を取り入れると◎。相手も安心して食事が楽しめるようになります。
外食では事前にメニューをチェック
外食のときは「何を頼むか」で毎回悩むより、事前にお店のメニューを確認して「食べられるものがあるか」を調べておくとスムーズです。好き嫌いが多い人は「選べない」ことで不安になりやすいので、事前準備で場の雰囲気がぐっと和らぎます。
「一口チャレンジ」でプレッシャーを減らす
「全部食べて」と迫るのではなく、「一口だけ試してみる?」と軽く勧めるのがおすすめ。無理に食べなくてもいいと伝えると、心理的ハードルが下がり、「思ったより平気だった」と克服のきっかけになることもあります。
食事以外の場面でフォローする
「好き嫌いが多い=愛情が伝わらない」なんてことはありません。大切なのは食事以外の部分でもコミュニケーションをとり、「食べられないこと=人格の否定」にならないようにすることです。料理にかけた時間や気持ちを認めてもらえるだけで、関係はぐっと安定します。
実際にうまくいった工夫の事例
-
調理法を変えたら克服できた
夫はトマトが苦手でしたが、ミネストローネに細かく入れたら「これは美味しい」と食べてくれるように。調理法を工夫するだけで、苦手意識がやわらぐこともあります。 -
外食前の下調べで安心
旅行先で好き嫌いが心配でしたが、事前に「食べられるメニューがある店」を調べておいたら、迷わず選べて雰囲気も崩れませんでした。 -
一口チャレンジで意外な発見
「絶対無理」と言っていたナスを、一口だけすすめたら「思ったより大丈夫」と反応が変化。それ以来少しずつ食卓に出せるようになりました。
.
大人になってからの好き嫌い事情
昔は苦手だった食材が食べられるようになるワケ
大人になると、「子どもの頃は大嫌いだったのに、今は大好物」という経験をする人が多いです。
ピーマンやゴーヤのような苦味のある野菜、ナスやしいたけのような食感に特徴のある食材はその代表例。
味覚は年齢とともに変化して、苦味や酸味を美味しいと感じられるようになることがあります。大人の特権とも言える“味覚のアップデート”ですね。
食の冒険で世界が広がる
旅行先や友人との外食で「人生で初めて食べたけど、美味しい!」と新しい発見をすることも。
例えば、タイ料理のパクチーや韓国料理のキムチなど、若い頃は敬遠していた香りの強い食材も、異文化に触れる中で「意外とクセになる」と好みに変わる人も少なくありません。
大人の食体験は、まるで旅をしているように新しい扉を開いてくれるのです。
逆に苦手が増えることもある
一方で、大人になってから苦手が増える人もいます。
ストレスや体調の変化で「脂っこいものが重たく感じる」「辛いものが胃に合わなくなった」といったケースも。
これは決してマイナスではなく、体が「今はこれが合わない」と教えてくれているサイン。無理に合わせる必要はなく、自分の体の声に耳を傾けることも大切です。
好き嫌いを共有する楽しさ
大人になると、食事は「ただ食べる」だけでなく人とシェアする時間の意味合いが強くなります。
「これ苦手なんだよね」「じゃあ私がもらうね」と笑い合ったり、
「昔は嫌いだったけど今は好きになった!」と話題にすれば、会話が広がるきっかけに。
食べ物の好き嫌いも、コミュニケーションのスパイスとして楽しめるのが大人ならではの魅力です。
あなたも当てはまる?大人になって食べられるようになったものチェックリスト
子どもの頃は嫌いだったのに、大人になってから「意外と美味しい」と感じる食べ物はありませんか?
下のリストから、自分に当てはまるものを思い出してみましょう。
-
ピーマンやゴーヤなど、ちょっと苦味のある野菜
-
ナスやしいたけなど、独特の食感がある食材
-
ブルーチーズや納豆など、香りが強い発酵食品
-
わさび・からし・からしレンコンなどの辛み調味料
-
コーヒーやビールなど、大人の味がする飲み物
チェックが多ければ多いほど、あなたの味覚は成長や経験を通して“アップデート”されてきた証拠。
食べ物の好みの変化は、大人になったからこその発見と言えるでしょう。
.
好き嫌いを受け止める工夫
言い方ひとつで場がやわらぐ
「これは嫌いだから食べない」と断るよりも、
「これはちょっと苦手で…でもこの料理なら大丈夫かも」とやさしく伝えると、相手の受け止め方も変わります。
言葉を少し工夫するだけで、場の空気がやわらかくなるんです。
食卓に“安心ゾーン”をつくる
好き嫌いがある人と食卓を囲むときは、「絶対に食べられるもの」を必ず一品用意しておくと安心感が増します。
「これなら食べられる!」という選択肢があるだけで、他の料理にもチャレンジする気持ちが芽生えやすくなるのです。
外食は“宝探し”気分で楽しむ
お店選びの段階から、「ここならあの人も楽しめそう」という視点で探すと、外食がちょっとしたイベントに変わります。
「このお店のパスタなら食べられるかも」「このカフェのスイーツはチャレンジできそう」――そんな発見は、まるで宝探しのようにワクワクします。
“一口だけ冒険”のすすめ
「無理に全部食べる」必要はありません。
でも「一口だけ挑戦してみよう」という小さな冒険は、食の世界を広げてくれるきっかけになります。
意外な美味しさに出会える瞬間は、大人になってからこそ味わえる楽しみのひとつです。
違いを楽しむという発想
「好き嫌い=欠点」ではなく、「人それぞれの個性」と捉えてみると、関係はぐっとラクになります。
「これが嫌いなの?私は大好きなのに!」という違いを笑い合えれば、食事の時間はもっと楽しくなります。
違いを“ネタ”に変えられた瞬間、好き嫌いはマイナスではなく、会話を盛り上げるエッセンスになるんです。
.
よくある疑問Q&A
Q1:好き嫌いが多いのは性格の問題?
A:いいえ、性格だけで決まるものではありません。
子どもの頃の経験や味覚の敏感さ、心理的な警戒心など、さまざまな要因が重なっています。「わがままだから」「頑固だから」と一概に判断するのは正しくありません。
Q2:大人になってから好き嫌いは直せる?
A:可能性はあります。
調査でも「昔は嫌いだった食べ物を食べられるようになった」という人は9割近くいます。調理法を変えたり、少しずつ慣れていくことで克服する人は少なくありません。ただし「無理に直す必要はない」と考える研究者もいます。大事なのは、無理せず自分に合う食生活を見つけることです。
Q3:食べず嫌いをなくすにはどうすればいい?
A:まずは「一口だけ試してみる」ことが効果的です。
苦手と感じる匂いや見た目も、実際に口にすると意外と大丈夫な場合があります。また、信頼できる人と一緒に食べると安心感が増し、挑戦しやすくなるとも言われています。
Q4:周囲に迷惑をかけない工夫はある?
A:外食や会食では、事前に「これなら大丈夫」と言える料理を確認しておくと安心です。
苦手な食材が多い場合は「食べられるものを中心にお願いしたい」と伝えるのも一つの方法。否定的な言い方ではなく、「これならOK」方式で話すと、周囲も受け入れやすくなります。
Q5:好き嫌いが多いのは悪いこと?
A:決して「悪いこと」ではありません。
人間にはそれぞれ感覚や経験の違いがあり、食の好みもその一部です。大切なのは、自分や他人の好き嫌いを否定せずに「違い」として理解すること。そうすれば食事の場がもっと気楽で楽しいものになります。
.
まとめ
食べ物の好き嫌いが多い人には、味や食感に敏感だったり、子どもの頃の食習慣が影響していたり、心理的に新しい食べ物に慎重だったりと、さまざまな背景があります。
時には人間関係で誤解を招くこともあるけれど、見方を変えれば「感覚が豊かで、自分に正直な人」とも言えるんです。
大人になると「昔は嫌いだったけど、今は大好き!」という発見もありますし、好き嫌いが会話のきっかけになって笑い合えることもあります。
つまり、好き嫌いは“マイナスな特徴”ではなく、その人の個性のひとつ。
大切なのは「食べられる・食べられない」で線を引くのではなく、違いを認め合って一緒に楽しむ工夫を見つけることです。
食卓に「これは絶対食べられる安心ゾーン」を置いたり、「一口チャレンジ」で小さな冒険をしてみたり。そうやって少しずつ歩み寄れば、食事の時間はもっと楽しく、ワクワクするものになります。
食べ物の好みは人それぞれ。だからこそ、違いを受け止めながら「今日はどんな発見があるかな」と楽しめる気持ちを持てたら、食卓も人間関係も、きっともっと豊かになりますよ。
📌本記事は筆者が調べた一般的な情報や考察をまとめたものであり、医学的な診断や治療を目的とするものではありません。
食生活や健康に関する判断は、ご自身の体調や専門家のアドバイスを参考にしてください。
関連記事
生活に欠かせない食事ですが、悩みは色々ありますよね。食べ方や冷凍に関する記事などたくさん執筆していますので、よかったら読んで下さいね。
📺綺麗な食べ方。口の動かし方。食べ方の綺麗な芸能人に学ぶ8つのテク!